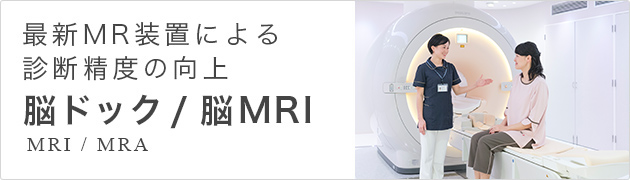輝くライフスタイルを応援する

No.133 Autumn.2018

未来は予測がつかないから
いつも笑って暮らしたい
エッセイスト・作家
阿川 佐和子さん
『ビートたけしのTVタックル』の進行役を務め、鋭い突っ込みと、その天真爛漫なキャラクターで国民的な人気を獲得した阿川佐和子さん。
昨年結婚して長年の独身生活に終止符を打ち、今年は介護をテーマにした著書『看る力』を出版するなど、新たな世界への挑戦を続けています。いつまでも少女のような愛らしさを失わない阿川さんに、60代を生き生きと楽しむための秘訣についてうかがいました。
取材・文/吉田燿子 撮影/齋藤久夫
スタイリスト/中村抽里 ヘアメイク/田中舞子(VANITES)
作家・阿川弘之さんの長女として生まれ、中高一貫の名門女子校に進学。大学卒業後はテレビの世界に身を投じ、報道番組の女性キャスターとして活躍した。

父は本当に怖かったんですよ。「いつ怒られるかわからない!」って、いつもビクビク。そのせいか、人の機嫌をうかがうようなところがあって。中学の頃「なんか、おどおどしているね」と友人に言われたこともあった。大学に進んでからも特にやりたいことは見つからず、ひたすら「父とは違う優しい穏やかな人との結婚」が目標だったんです。
ところが20代終わりに、たまたま朝の報道番組のリポーターを務め、さらに89年からは『筑紫哲也NEWS23』で、筑紫さんのアシスタントを担当したんです。私って本当はバカなんですけど、見た目は賢そうというタイプで(笑)。「阿川弘之の娘なのに、こんなことも知らないの?」とは絶対に言われたくない! 周囲のイメージを壊すまいと、無理してました。
自分自身が解放された
『TVタックル』での仕事
女性キャスターとして、順風満帆のキャリアを歩んでいた阿川さん。転機が訪れたのは39歳の時のことだ。自らの意志で『NEWS23』を降板し、渡米して1年間ワシントンに滞在。帰国後は小説・エッセイやテレビ番組の司会、インタビュアーなど、幅広い分野で才能を開花させてゆく。
『NEWS23』の降板を決めた時、周囲からはいろいろ言われました。「親や筑紫さんの七光りを棄てて、自分に何が残ると思っているんだ」「今後一切、仕事が来なくなるかもしれないぞ」と。
でも、1年間の滞米生活を終えて帰国した時、「一緒に仕事しませんか」という人が現れたんです。何の肩書もなくなった素の私を見て、「一緒に仕事したい」と思ってくれるのなら、その期待に応えよう――そう思った時、肩の力が抜けたような気がしました。
その後、テレビの仕事に復帰したのですが、どうも自分にテレビの仕事が向いているとは思えない。そろそろ潮時かな、と思っていた矢先に、『ビートたけしのTVタックル』の進行役をやらないか、という話をいただいたんです。
初期の『TVタックル』は柔らか目の企画が多かったのですが、小泉政権が誕生すると、政治ネタを採り上げるようになりました。それを機に、与野党の政治家や政治評論家が、大挙して番組に出演するようになったんです。ところが、政治家の皆さん、なぜか『TVタックル』に出ると、油断してワキが甘くなるんですね。政権交代で大臣になった民主党の政治家に、「野党の時は、そんなこと言ってなかったじゃない?」と突っ込むと、現大臣が「アガワさん、きついよ」なんて言われて。政治家の人間臭い面がポロっと出てしまうんですね。そんな番組の面白さが受け、私もたけしさんを後ろ盾にして、政治家相手に自由にモノが言えるようになった。
この番組の仕事を通じて、私自身も解放されました。私は報道系の番組が長かったので、どうしても堅物に見られがちだったんです。でも、バラエティ番組はふとした瞬間に、素の自分が出てしまう。周囲の私を見る目も変わり、ものすごく楽になりました。それまでは、一見優等生に見えるけれど、知識が豊富でもなければ、政治経済のこともよくわからない。そんな自分をごまかすことに汲々としていましたから。
番組を仕切るのは大変。司会だけでなくインタビューの仕事もいまだにうまくいかないことだらけ。でも、一緒に仕事をする人たちと役割分担しながら、よいものを作り上げるのがこの仕事の醍醐味。「この仕事で私は何をするべきなのか」と考えている時間が一番好きですね。
昨年5月結婚。独身生活に終止符を打ち、新たなライフステージへと踏み出した。
元々、私は結婚願望が強くて、専業主婦になるのが夢だったんです。結婚したら自分の人生はどんなふうに変わるのかしら、と楽しみにしていたのですが、60歳過ぎての結婚は全くそんなものではなかったですね。互いの生活のペースや、大切にしているものには、なるべく触らない。触る必要がある時には、互いに調整しながら生きていく、という感じです。
とはいえ、他人同士が一つ屋根の下で生活するわけですから、少しは譲り合うことも必要です。タオルのかけ方一つ、トイレの蓋の開け閉め一つにしても、生活習慣はそれぞれ違いますから。朝、目玉焼きに黒胡椒をかけたら、「僕は白胡椒の方が好き」。それを聞いて「こんなに趣味が合わないとは思わなかった。なんでこんな人と結婚したんだろう」と。もはや、燃え上がるものは何もない。手をつなぐのも「転ばないため」(笑)。
でも、家に帰った時、相手がいてくれるとホッとする。たとえて言うなら、整腸剤みたいな感じかな。飲んですぐ効果があるかどうかはわからないけれど、安心する感じがあるでしょう?

介護を乗り切る秘訣は
「後ろめたさをもつこと」
2015年、父・阿川弘之さんを病院で看取り、認知症が進む母の介護も経験。その経験を元に、今年6月、青梅・よみうりランド慶友病院の創立者である大塚宣夫医師との対談をまとめた介護入門著書『看る力』(文春新書)を出版した。
親の介護をしていると、心のどこかで「滅私奉公している」という気持ちが出てくるんですね。自分の仕事や生活を犠牲にして親のためにご飯を作り、必死で世話をする。なのに「あんた、もう帰ってよ」と言われると、「なんて報われないんだろう」と思って悲しくなっちゃう。疲れが100倍になって返ってくるわけです。
うちの母は認知症ですが、変わっていく親の姿を目の当たりにするのもつらい。「あの完璧だった母が、こんなに壊れちゃったのか」と思うと、本当に情けなくなります。元の親に戻ってほしいけれど、それは叶わない。「人間生きていれば、誰もがいつかはそういう道を辿るんだ」と、引いて見られるようになるまでは少し時間がかかるんですね。自分に余裕がないと人に優しくなれない。だからこそ私は「後ろめたさをもつ」ことが大切だと思うのです。
例えば、ゴルフ帰りに母のところに寄り、「ちょっと仕事が忙しくて……」と言い訳すると、母も「忙しいのに悪いわね」と言うんですね。そうすると後ろめたい気持ちになって、母に優しく接することができる。要は、浮気をしている亭主が奥さんに優しいのと同じ心理ですよね。介護の疲れを軽減するためにも適度に息抜きして、余力を残しておくことが大切だと思います。
自分も歳を取れば、いつかは介護される側になる。東京五輪開催年の2020年には、日本では50歳以上の女性が過半数を占めるといわれています。高齢者だらけのこの国で、老いの日々をどう楽しむか。本気で考える必要があるのではないでしょうか。
故・井上ひさしさんとお会いした時、こんな話を伺いました。井上さんが南の島を訪れた時、飛行機が欠航になり、別の飛行場までバスで移動しなければならなくなった。ところが渋滞にはまり、バスが1センチ刻みでしか動いていないようで――。皆が不機嫌になりかけていた時、ある乗客がこう言ったそうです。「これが本当のセンチメートル・ジャーニーですね」って。
すると皆がどっと笑い、不機嫌な気分は一気に吹き飛んでしまった。「笑いには一瞬にして場の空気を変える力がある。ちなみにそう言ったのは僕なんですけどね」と、井上さんは言っておられました(笑)。
老後のことを考えると、どんどん暗い気分になってしまうけれど、笑えばスッと楽になる。私は大好きなゴルフをやりながら、「ナイスショット!」と言って振り向いた瞬間に死にたい。でも、それは99%無理。未来のことは予測がつかないから、自覚がある限りは笑っていたいと思いますね。いつまでも豊かな感受性を失わず、笑顔で暮らしていたい。私、そんな人生を送りたいと思っています。

Profile
あがわ・さわこ
エッセイスト、作家。1953年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部西洋史学科卒。『ああ言えばこう食う』(檀ふみとの共著、集英社)で講談社エッセイ賞、『ウメ子』(小学館)で坪田譲治文学賞、『婚約のあとで』(新潮社)で島清恋愛文学賞を受賞。2012年『聞く力』(文春新書)が年間ベストセラー第1位に。14年菊池寛賞を受賞。テレビでは『ビートたけしのTVタックル』(テレビ朝日系)、『サワコの朝』(TBS系)に出演中。
『看る力』アガワ流介護入門 (文春新書)
父・弘之氏を看取り、認知症の母をケアする阿川さんが、自らの介護経験を元に、高齢者医療の第一人者・大塚宣夫医師と大いに語り合った阿川流「介護本」。