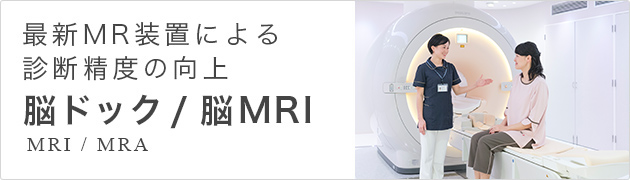輝くライフスタイルを応援する
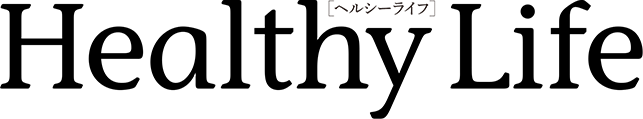
No.124 Summer.2016

終戦という原体験が 僕の背中を押してくれた
解剖学者
養老 孟司さん
空前のベストセラー『バカの壁』を世に送り出し、“唯脳論”を提唱して、現在の脳ブームの先駆けとなった養老孟司さん。
理系と文系の学問の統合を目指し、幅広い分野で執筆活動を行ってきました。
78歳になった今も、その知的好奇心は衰えることをしりません。
現代の“知の巨人”はいかにして生まれたのか。その背景に迫ります。
取材・文/吉田燿子 撮影/本多康司
子供の頃から大の虫好きだった。鎌倉の豊かな自然の中で育ち、昆虫採集や川遊びに熱中。だが、のどかな日々にも戦争は影を落としていた。終戦を迎えたのは小学2年の時。それは孟司少年にとって、その後の人生を決定する強烈な原体験となった。
終戦という体験がどんなものだったか、今の人は想像がつかないと思います。それまでは「一億総本土決戦」「無敵皇軍」、負けるわけがないと教えられてきた。それがある日突然、「日本は戦争に負けました」となり、教科書の軍事色が強かったり、戦意を駆り立てるような部分は墨で塗りつぶすように指示されたんですから。「何これ」という感じですよ。
そうなると、人の言うことや新聞やラジオの報道は信じられなくなる。その世代が向かったのが、モノ作りです。例えば『プロジェクトX』に登場する技術者たちが、なぜ一生懸命トンネルを掘ったり車を作ったりしたか。それは「モノ作りは人を騙さない」からです。作った車が動かないのは自分のせいであって、誰のせいでもない。モノは嘘をつかないですからね。
医療事故をきっかけに解剖学者の道へ
4歳で父を亡くし、小児科医の母の影響で医師を志した。東京大学の医学部に進学したが、インターン時代に医療事故に遭遇。それをきっかけに、解剖学者としての道を歩むこととなる。
当時、医療事故は珍しいことではありませんでした。特に東大病院は、多くの病院から見放された患者さんが最後に来るところでしたから。朝、入院してきた子供が、夜、亡くなって出て行くなんて当たり前だった。解剖学者になった理由の一つは、生きた患者さんを診ると不安でしようがないからです。だって、注射を1本間違うだけで人は死んでしまう。手術室に入れば「このメス、大丈夫かな。汚れてないかな」。考え出したらキリがないわけですよ。
そこへいくと、解剖は、昨日進んだところできちんと終わっている。自分がやったことしか目の前にないんです。患者さんの体はどんどん変化しますが、死体というのは、自分が働きかけないかぎり何も起こらない。解剖をやっていると、何か安心だなあと思っていたのですが、後になって「そういうことか」と気がついた。

〝唯脳論〟で脳ブームを巻き起こす
東大大学院で解剖学を学び、医学博士号を取得。学内が安保闘争で騒然とする中、東大助手として全共闘との交渉の矢面に立った。1981年、東大の解剖学第二講座教授に就任。順風満帆なキャリアとは裏腹に、自らの進むべき方向を模索する日々が続いた。
当時は学会が米国流になっていった時期で、論文もどんどん書かないといけない。古典的な解剖学は論文にはならないので、「これじゃあ、うまくいかないよな」という気持ちがありました。
僕と同世代で、分子生物学の道に進んで成功したのが、ノーベル生理学・医学賞を受賞した利根川進さんです。分子生物学というのは理屈の世界ですから、論理的に解を導き出すことができる。でも、僕は理屈で説明できるものには興味がなかった。虫みたいに、不思議でしようがないものが好きなんです。「なんで、こんな生き物が世の中に存在するんだ」というのは、理屈で説明できないでしょう。その方が面白いですから。
養老さんは独自の方法で思索を深め、それは著述という形で結実する。1989年『からだの見方』でサントリー学芸賞を受賞。同じ年に出版した『唯脳論』は、その後の脳ブームの先駆けとなった。
脳を動かすのは「外界からの刺激」なんです。脳が情報処理装置だとすれば、入力装置は五感で、出力装置は筋肉運動です。一歩歩くたびに景色が変わり、それが視覚を通して、どんどん脳に入力されていきます。
だから、子供はまず動き出さないと学習しません。まだハイハイもできない赤ちゃんにビデオを見せても、なんの学習にもならない。まず自分が動くことによって、五感が周囲の変化を感じ取り、それが脳に入力されて、いろいろなことを学んでいくわけです。脳の成長はループ状で成り立っている。トライ・アンド・エラーを繰り返さないかぎり、人間は学習できないんです。
東大教授を退官し、著述活動を本格化
1995年、養老さんは再び人生の転機を迎える。定年を前に、57歳で東大を退官したのだ。北里大学で教鞭をとるかたわら、著述活動を本格化。この決断が、後の活躍に結びついていくこととなる。
東大を辞めたのは、完全に煮詰まってしまったからです。定年まであと3年しかないし、これ以上大学にいても新しいことはできないだろうと。もともと、55歳になったら辞めようと思っていたんです。55歳ならまだ次の職があるし、あと10年は仕事ができる。10年あれば、もうひと仕事できますから。
研究で成功して世界に認められるためには、利根川さんのように世界共通の研究課題に取り組み、英語で論文を書かなきゃいけない。利根川さんがグローバル企業なら、僕はローカル企業。ローカルとは、例えば「日本語でしか書かない」ということです。僕は、英語は得意な方だったけど、英語で書くのはもうやめようと思った。なぜなら、本当にものを考えることは母国語でしかできないからです。周囲の学者が皆「英語で書かなきゃだめだ」と言っている時に、「俺は日本語で書く」と決めた。終戦の体験に背中を押されて、我が道を行くと決めたんです。もちろん、そんなことを言ったら学界で干されるので、周りには言いませんでしたが(笑)。

「社会脳」と「自然脳」のバランスが大切
解剖学研究にもとづき、身体・脳を中心として社会や文化の問題を考え、理系と文系の学問の統合を目指す――それが、養老さんの新たな目標となった。65歳の年に『バカの壁』を出版。これが大ベストセラーとなり、「養老孟司」の名は全国に轟いた。以後、養老さんは日本を代表する「知の巨人」として活躍の場を広げていく。
人間には「社会脳」と「自然脳」があります。「社会脳」とは人間を相手にしている時に働く部分ですが、数学の問題を考え出すと、途端に脳の違う部分が働き始める。これが「自然脳」です。
この2つの脳のバランスが崩れると、いろいろな問題が起こる。その典型ともいえるのが、米国のスペースシャトル、チャレンジャー号の爆発事故でしょう。打ち上げの日、つまり事故があった日は異常な寒波で、部品が硬くなり、ロケットがうまく作動しない危険があった。それで、技術者たちは発射の延期を主張した。ところが、上司が「すでに何度も発射を延期しているから」という理由で、発射を強行してしまったんです。その上司は広報部門でした。技術者が自然脳だとすれば、広報は典型的な社会脳。人間社会や組織では、社会脳が優先する。社会脳がデフォルト設定なんです。
大きな組織では、どうしても社会脳が優先してしまう。だから、技術者が興した本田技研工業やソニーのような会社は、成長して大きくなると、社会脳が優先して本来の姿を失ってしまう傾向があります。大切なのは、「社会脳と自然脳の2つがある」ということを知り、両方の脳をバランスよく活性化すること。自然脳が強い人も、社会脳を鍛えなくてはいけません。自分が得意な方だけを使って、楽をしてはいけないんです。僕は、自然脳は虫との対話の中で、社会脳は大学の中で喧嘩しながら磨きました(笑)。
都会にいると、どうしても社会脳に支配されてしまう。そうならないためにも、1年に3カ月は田舎に行って働くことをお勧めします。僕はこれを「参勤交代」と呼んでいるんですが、自然の中に身を置いて身体を使いなさい、ということです。1日15分でいい、虫でも石でも何でもいいから、「人間が作らなかったもの」に触れる時間を作ってほしいと思います。
Profile
ようろう たけし
1937年神奈川県鎌倉市生まれ。解剖学者・医学博士・東京大学名誉教授。1963年東京大学医学部卒業後、東京大学医学部教授、北里大学教授を歴任。長年の解剖研究の結果から、身体および脳を中心として、社会、文化の問題を考える“唯脳論”を提唱し、理系と文系の学問の統合を目指している。文学方面にも活動の幅を広げ、本来の虫好きも高じて、以前から取り組んでいる環境問題にも力を注ぐ。著書『バカの壁』は400万部を超える大ヒットを記録。
健診に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。